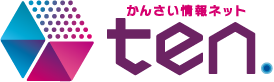3月16日(水)
【記者解説】JR西日本春のダイヤ改正“過去最大規模の減便”地域にもたらす影響は?
JR西日本は3月12日のダイヤ改正で、過去最大規模の減便に踏み切りました。
その要因はやはり、「新型コロナ」。JR西日本の収益はコロナ前の2019年と比べると、
2020年には半分ほどに減少。特に全体の収入の半分を担っていた新幹線が、
3分の1ほどになっているのです。
ほかにも、人口減少や自然災害など、鉄道会社には、今、さまざまな逆風が吹いています。
そんな逆風に立ち向かう手はあるのか…ニースのウラ側を知る担当記者の「記者メモ」から
紐解きます。
JR西日本今回のダイヤ改正で過去最大規模の減便

JR西日本 春のダイヤ改正のウラ側を記者が解説
JR大阪駅北側の再開発エリアに来年春開業する「うめきた新駅」。“顔認証”で通過できる改札など、“最先端技術”を取り入れる予定です。未来のサービスに期待が広がる一方、足元のコロナ禍で経営状況が悪化しているJR西日本。今回のダイヤ改正で“過去最大規模の減便”に踏み切りました。その影響と背景を記者が解説します。

昼の新快速が減便したJR西日本近江八幡駅
JR琵琶湖線の近江八幡駅では、昼の時間帯の一部で新快速が2本から1本に減りました。
(利用客の男性)
「いつもの感覚で(電車が)あると思っていたんですけど、なくて30分ぐらい待っています。思っていたより不便かなと…」
(利用客の女性)
「通勤時間帯だけあればいいと思いますけどね。(移動は)ほとんど車ですもんね」
地元の企業からは不安の声もあがっています。

地元不動産業者 近江ハウジング 代表取締役 黒田 充彦さん
(地元の不動産業者・近江ハウジング 代表取締役 黒田 充彦さん)
「今回、昼間とはいえ新快速が減便したというのは、結構インパクトがあります。(新快速が減った地域は)今後の発展という意味ではどうなんだろう?というイメージをもたれると思います。中長期的にみれば影響がジワジワ出てくるのではないでしょうか…」
鉄道の減便は地域経済にも影響が

中谷しのぶアナウンサー・右:岡村真朋記者(読売テレビ)
(中谷しのぶアナウンサー)
Q.過去最大規模の減便ということで、その影響は大きいのでしょうか
(岡村記者)
「国鉄が民営化する直前からの乗車人員の動きをみますと、各エリアで新しいベッドタウンなどができて、(人が増えて)そのエリアの発展とともに、JR西日本は新快速といった列車を使って多くの人を速いスピードで輸送してきたということがみて取れます。ですので、今回の減便も少なからず影響があると思います」

イメージの悪化を懸念する不動産業者 近江ハウジング 代表取締役 黒田 充彦さん
Q.影響があるのは、鉄道を使う人だけではないということでしょうか?
(岡村記者)
「今回、昼の時間帯に1時間2本だったのが1本に減便したんですが、不動産事業者からは、物件を買うときに『利便性が悪くなった』というマイナスイメージが定着すると、なかなか(そこに住もうという)最終判断にならないのではないか、という懸念の声が聞かれました。鉄道というのは、その地域の経済にも大きくかかわるものですので、今後、減便が地域にマイナスに影響する懸念があります」

コロナ禍で打撃「新幹線」
Q.鉄道の整備とその街の発展というのは連動しているものと言えますが、減らさざるを得ないのは、コロナ禍の影響が大きかったと言えるのでしょうか?
(岡村記者)
「今回、コロナ禍で運輸業界は苦しい状況にありますが、特にJR西日本は影響が大きいのは新幹線事業だと言っています。運輸収入全体ではコロナ禍前の2019年度から半減しており、その中でも新幹線事業は6割減と大きく落ち込んでいます。」
Q.旅行や出張をする人が減ったからでしょうか?
(岡村記者)
「そうです。実際グラフを見るとコロナ禍という状況になって以降、時折回復傾向はみられますが、新幹線の利用状況はほとんどの期間で50%を切っており、ほとんど乗客が戻ってきていません。もともと安定していた事業で利益を上げられなくなったということが、経営状況悪化の要因の一つと言えます」
鉄道事業を圧迫するする補修・災害・事件

事業を圧迫する安全面の投資増
Q.ほかにもJRの事業を圧迫しているものがあるのでしょうか?
(岡村記者)
「鉄道は安全が一番大切です。その中で、線路や橋の補修が非常に重要です。列車が運航していない時間に補修・点検作業にかなりの時間を割いています。最近は自然災害が多く、その影響で線路や橋が傷んでいるという事があり、普段より作業量が増えているという状況もあります」
Q,相次ぐ事件の影響もあるのでしょうか?
(岡村記者)
「そうです。列車内で起きる事件や事故によって、防犯カメラをはじめ、車内での安全を守るといった分野にも投資をしていかなければならず、その影響もあります」

存続のため上下分離方式をとった近江鉄道(滋賀県)
Q.投資であり、負担でもあると思いますが、工夫している会社もあるんですよね。
(岡村記者)
「実際に取材したエリアがありまして、滋賀県を走っている近江鉄道は、120年の歴史がありながら、経営状況が悪化して事業継続が困難になりかけていました。そういう状況下で“上下分離方式”という手法を使って存続しています」

上下分離方式や無人駅の簡素化で経費を縮小
Q.上下分離方式とはどういったものなんしょうか?
(岡村記者)
「鉄道事業というのは、列車の運行や駅舎を含めた施設、周辺地域の開発も一社で担っていたものを、経営状況が厳しくなったときに、列車の運行だけを鉄道会社が行って、線路や駅舎の維持管理は周辺自治体に負担してもらうという制度になります」
Q.ほかにも工夫はありますか?
(岡村記者)
「JR西日本でもコスト削減に取り組んでいることがあって、利用客の少ない無人駅の駅舎自体をコンパクトにすることにより、面積が小さくなりますので、固定資産税や維持管理の経費も削減できるといった例もあります」

利便性を求める人たちに一定の負担
Q.小さな工夫の積み重ねながら生き残りの模索をしているという事ですね。
(岡村記者)
「コロナ禍という事もあって、鉄道を巡る状況が大きく変わろうとしている中で、今後の課題として見えてくるのが、利便性を求める人たちに一定の負担が課されるのではないかという事です。コロナ禍以前ですと、地方のローカル線を中心に、維持をどうしていくかという議論があったんですが、このコロナ禍で都市部に近いエリアの鉄道事業にもいろいろな影響が出てきて、今後は、利便性を求めて住んで、鉄道を利用している人たちに、例えば運賃が上がるだとか、今まで通りのまま、利便性を享受できなくなる可能性があります」
(「かんさい情報ネットten.」 2022年3月16日放送)
ホームページ上に掲載された番組に関わる全ての情報は放送日現在のものです。あらかじめご了承ください。