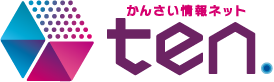7月18日(月)
【孤立させない】36人の命が奪われた京アニ放火殺人事件から3年 求められる被害者支援とは
36人が犠牲になった京都アニメーション放火殺人事件から3年。月日が流れるとともに、事件の被害者に対する支援の難しさは表面化し、そのあり方が問われ始めています。本当に必要な支援とは何なのか?事件で妻を亡くし、小学生の息子と2人で歩む遺族を取材しました。
【特集】京アニ事件から3年、4年目は周りの人と共に…残された父子で歩む“日常” 被害者を孤立させない支援のカタチとは―

人気アニメの作画監督を務めていた寺脇晶子さん(当時44)
2022年7月18日で、36人が犠牲になった「京都アニメーション放火殺人事件」から3年となりました。
復職を果たした社員もいるほか、4月には15人ほどの新入社員が入社。京都アニメーションは再建への歩みを進めています。しかし、3年という月日が流れ、事件の被害者に対する支援の難しさも表面化しています。妻を亡くし、小学生の息子と2人で歩んできた遺族を取材しました。
残された父子で歩む“日常” 息子を思い「あえて厳しく」接してきた父

晶子さんが結婚式のために描いた絵
あの日、失われた36人の命…。被害にあった寺脇晶子(てらわき・しょうこ)さんは、当時44歳。人気アニメ『響け!ユーフォニアム』、『涼宮ハルヒの憂鬱』などで、作画監督を担当していました。アニメファンにその名前を広く知られていた晶子さん。結婚式のために描いた絵も一切、妥協しませんでした。
「凝りに凝っていましたね。これを描くためだけに、花柄の穴を開けるパンチを買いに行ったり…ほんまに、妥協せんかったな。仕事に関しては、もっとでしょうね」(寺脇譲さん)

妻を亡くした寺脇譲さん、息子と2人で暮らす
夫の寺脇譲(てらわき・ゆずる)さんは、小学5年生になる息子と2人で暮らしています。この日は、2人並んでキッチンに立ち、寺脇さんの手ほどきでカレーを作っていました。
「あちっ」(息子)
「やけどすんなよ」(寺脇さん)

息子の勉強机…かつては晶子さんが使っていた
寝室にある机は、晶子さんが生前に使っていたものです。今は息子の勉強机になっています。
「作品を評価して頂いていましたが、『自分は絵を描くのが下手だ』といつも言っていました。ふと夜起きたりしたときに電気が付いているので、『どうしたん?』と言ったら、『うーん、ちょっと練習している』って…」(寺脇さん)
事件当時、小学2年生だった息子は、時間の経過とともに母との思い出を語るようになりました。
「キャンプファイヤー。あそこでさ、マシュマロを焼いて、みんなで食べて…」(息子)
「みんなで、ママもよく行ったもんな」(寺脇さん)
「(ママは)どっちかというと優しかったかな」(息子)
「ママは優しかったな…」(寺脇さん)

「息子が母親のことを自ら話すようになった」
「2年半ぐらいしてから、息子が母親の事を自分から話すようになってくれたんです。母親とこうした、ああした、と言ってくれるようになったのは、彼にとって気持ちや心境が大きく変わったからかなと思います」(寺脇さん)
社会的反響が極めて大きかった事件。この3年は息子の将来を思い、寺脇さんはあえて厳しく接し続けました。
「一番大事なのは、何かあったとしても自分で這い上がれる力。自分で這い上がって、自分で前を向いて歩く力。まだこの年じゃ無理やけど、少しでもその芽を育ててあげるというのもまた親の責任かな…まずは子どもがしっかりと前を向けたことを確認して安心してから、自分かなと思います」(寺脇さん)
仕事に、家事に、育児に…走り続けてきた3年間。無理がたたったのか、寺脇さんの肺には膿がたまり、入院を余儀なくされました。
「普通にパパが会社に行っているときも一人やし。なんか…めっちゃ静かやった」(息子)
たった一人で夜を過ごした、小学5年生の息子。翌日、譲さんは1日3回の通院を条件に、退院を許可されました。「息子と一緒にいたい」という思いから病院を説得したのです。
初めて頼った外部の「支援」 母と、周りの人も一緒に、前へ…

張りつめていた表情が少し和らぐ
この日、寺脇さんの家を訪れたのは、行政の職員や、子育てに悩む家庭の支援を担うNPO法人のスタッフ。病院から連絡が入り、親子を心配して訪問しました。面談の中で、寺脇さんは最近の気持ちについてアンケート用紙に記入していきます。『自分の気持ちにゆとりがあるか』という問いには…。
「…ゆとりはないわなあ」(寺脇さん)
「今はそうですよね。お体のこともありますからね」(職員・NPO法人スタッフ)
悩みや聞いて欲しいことなどを自由に書く欄には、『子どもと2人で孤立していないかが心配』と、父親としての切実な思いが書き綴られました。
「誰かが自分の事を思ってくれているというか、必要としてくれているじゃないですけど。気にかけてくれている、存在を認めてくれているという人が、一人でも世の中にいると思えたら僕はうれしい」(寺脇さん)
初めて外部からの支援を受け入れた寺脇さん。張りつめていた表情が少しだけ、和らぎました。
「すみません。また頼らせてもらいます」(寺脇さん)
「ぜひぜひ、遠慮なさらないでくださいね」(職員・NPO法人スタッフ)
今後は週に1回、おにぎりを持ってきてくれることになりました。2人を孤立させないための“支える形”です。
「『支援』って日本語だと、支えて援助するとしか書かないんでしょうけど、助けてもらうっていうのは、“ヘルプミー”ではなくて、“コミュニケイト”なのかな。助けてもらうやり方というのも千差万別いろいろあるのかなと。その人に適した内容を考えて、助けてもらったらいいかなって思いました」(寺脇さん)

母と周りの人と共に歩みはじめた4年目
以前よりも、親子の時間を大切にするようになった2人。週末はスイミングに行き、帰り道にお弁当を買って一緒に食べます。
「どない?」(寺脇さん)
「おいしい」(息子)
「おいしい?今年は桜も見に行ったな。忘れてないよな?」(寺脇さん)
「うん」(息子)
「何回かママと花見したん覚えてる?まだ小さかったからな…」(寺脇さん)
3年間、親子2人で走ってきました。これからは…母と、周りの人と、共に歩いていきます。
「4年目は・・・ちょっと子どもにも余裕を与えたいし、優しくしたい。僕自身も肩の荷を少しだけ下ろそうかなって…」(寺脇さん)
(「かんさい情報ネットten.」 2022年7月18日放送)
ホームページ上に掲載された番組に関わる全ての情報は放送日現在のものです。あらかじめご了承ください。