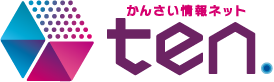3月8日(火)
【震災から11年】「被災者ではない僕だから」
東日本大震災から、まもなく11年。被災地の岩手県釜石市に一昨年移り住んできた兵庫県神戸市出身の男性がいます。男性は、震災の当事者ではなくても出来ることはあると活動しています。その姿を取材しました。
(かんさい情報ネットten. 2022年3月8日放送)
【特集】東日本大震災から11年 「被災者ではない僕だから」 神戸から釜石に移住して活動する男性が思う”できること“

雪の中 高齢者を訪問する男性
東日本大震災から11年、被災地の岩手県釜石市に阪神・淡路大震災の被災地神戸市から移住してきた若者がいます。神戸の震災の時は生後9か月で当時の記憶はないという男性ですが、東日本大震災で被災した人たちに寄り添う活動を続けてきました。なぜ東北の被災地にこだわるのか…その理由とは。
阪神淡路大震災は記憶にないが…
一人の男性がある高齢者のお宅で声を掛けます。
「お母さーん、これ頼まれたもの…」

東日本大震災の被災地で活動する久保力也さん
久保力也さん・27歳。2020年岩手県釜石市に引っ越してきました。久保さんが生まれ育ったのは、阪神淡路大震災の被災地・兵庫県神戸市です。地震が起こった1995年1月はまだ生後9ケ月で当時の記憶はありません。
(久保力也さん)
「母親から聞いた話で、オムツやミルクが必要な中、近所の人が『久保さんの赤ちゃんがいるのなら持って行ってあげよう』と言って、わざわざ持って来てくれたり、いろんなところからの支援があって、もしそれがなかったら自分がその時体調を崩していたかもしれないと思ったことが、本当にいろんな人から助けられて、今の自分があると考えるきっかけになったんです」

全国で初めて防災専門学科が設置された兵庫県立舞子高校(神戸市)
徐々に復興していく神戸の街を見ながら育った久保さんは、阪神淡路大震災の教訓を繋ぐことを目的に全国で初めて「防災専門学科」が設置された兵庫県の高校に進学します。高校1年生の3月、あの日を迎えました。
東北地方を襲う激しい揺れ…「東日本大震災」です。
ボランティアとして被災地を訪れて…

高校生の時ボランティアとして初めて被災地を訪れる
久保さんが被災地に初めて足を踏み入れたのは、震災発生から2か月後でした。被災地にボランティアで訪れ、あまりにも大きい被害を目の当たりにます。その後、大学生になっても岩手県や宮城県の被災地を中心に足を運び続け、その数は100回以上にもなりました。こだわったのは被災した人たちの話を直接聞くことです。

当時の久保さんのことを語る被災者の男性
(久保さんが高校生の時訪れた被災者の男性)
「高校生の時は、遊びたい盛りなのに、そういう時に時間を割いて泥を取りに来てくれたから、すごくうれしかった。その後も自分でアルバイトしたお金を使ってこっちに来るから、すごいなと思っています」

被災者の体験談に涙を流す学生
久保さんは、語る場がなく、きっかけを掴めずにいた同世代の被災者が震災の体験を打ち明けられるように、関西の学生との交流会を開きました。
一人の学生が涙を流しながら話に聞き入っています。

被災の体験を語る千葉則文さん
(宮城県石巻市で被災した千葉則文さん)
「震災にあったときに、友達を一人…女の子なんですけど…死…」
“死”という言葉の後、次の言葉が出ません…目頭を押さえ、沈黙の後、ふり絞るように続けます。
「その女の子なんですけど、実際一人で逃げていれば助かったはずなんですが、その家に当時“半身不随”のおばあさんもいたらしくて『おばあさんを助けなきゃ』と言って、そのまま津波に飲み込まれてしまいました…」
(久保さん)
「語ってくれた人の思いというのは、『同じことを繰り返したくない、その人には同じ思いをしてほしくない』という“思い”があって伝えてくれているので、その思いを無駄にしないためには、自分も同じように“語り部”として誰かに発信していく必要がある…」

今まで行った講演は300回を超える
久保さんは、話してくれた人の思いを受け取って、語り継ぐという自分に課した使命を果たそうと講演を行ってきました。その数はすでに300回を超えます。
生活拠点を釜石に 被災者とともに歩む

久保さんが拠点を移した釜石市
2020年、ついに久保さんは震災以来何度も足を運び、いっしょに活動する仲間もできた釜石市に、生活の拠点を移しました。
(久保さん)
「子どもたちにとっては知らないことだけど、親から聞く、友達・知り合いから聞く、まちの復興の様子も見ているという中で、自分は当事者じゃないけれど、何かしたいとか、やらないといけないかもしれないとかというところが、(自分と)似ている境遇なので、何か一緒に動くことができるだろうと…」

塾の生徒と談笑する久保さん
久保さんは、自宅で学習塾をしながら、街の復興とともに育ってきた子供たちのために自分が伝えられることを探しています。
(学習塾に通う生徒)
「話の中身も結構面白くて、雑談も楽しいしわかりやすいです」
(久保さん)
「そう言うしかないですからね、本人を目の前にして、『あの人分かりにくい』とは言えないですよ」
そういって二人は楽しそうに笑います。
震災の経験がない人に、命を守る防災への意識をどう高めてもらうのか、今取り組んでいるのは、“帰宅困難時”や“避難所での生活”を模擬体験してもらう一泊二日の「防災キャンプ」です。2022年の夏に全国数十か所で開催できるように被災経験のない学生も巻き込みながら、計画を進めています。

東日本大震災の被災地で活動する久保力也さん
久保さんは被災地に身を置いて、大切な人や場所をなくした人たちの中で、当事者ではない自分が活動することに葛藤した時期もあったといいます。
(久保さん)
「いろいろな活動をしている中で、被災体験の有無みたいなところで、自分がここにいていいんだろうか、話が合ってないんじゃないだろうかとか、いろいろ思うところはありましたが、今は、全くそんなことはなく、外から入ってきているので、既存のものも大切にしながら新しい風邪を起こすのが僕の役割だと思っています」

この場所でやってみたいということに感謝
この日、久保さんは被災した高齢の女性を訪ねました。
(被災者の女性)
「だまされるなよ、という人もいるけど、何をだまされるの? (この場所で)やってみたいって言ってくれる人がいてくれたことに感謝ですね」
いま久保さんは「震災の記憶がない自分だからできることがある」と信じています。
(読売テレビ 「かんさい情報ネットten.」 2022年3月8日放送)
ホームページ上に掲載された番組に関わる全ての情報は放送日現在のものです。あらかじめご了承ください。