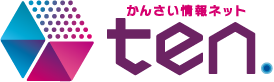5月24日(火)
600万人超と言われる認知症、40代で発症した男性と妻の記録「死んだ方が、いっそ楽かな…」絶望の淵で見つけた希望とは―
“持続可能な開発目標”「SDGs」今回は“すべての人に健康と福祉を”。
京都市北区の下坂厚さん(48)は2年前、若年性認知症と診断されました。異変に気付いたきっかけは、いわゆる“もの忘れ”。働いていた鮮魚店で、注文を忘れたり、職場の同僚の名前がわからなくなったのです。仕事に自信も出てきた働き盛りの40代。住宅ローンも残っていました。「目の前が真っ暗になった」という下坂さん。一時は「死んだ方がいっそ楽かな」とも考えたといいます。そんな下坂さんを、絶望の淵から救ったものとは?進んでいく症状を抱えながら「認知症になっても終わりじゃない」と語る下坂さんの生き方を、取材しました。
【特集】「私のこと、まだわかる?」胸に刺さる妻の言葉…40代で若年性認知症を発症した男性が絶望の淵で見つけた希望―

若年性認知症の夫と妻の記録
2025年には、患者数が700万人を超えるとも言われる「認知症」。高齢化が進む日本の国民病とも言われ、高齢者に多い病気ですが、若い人にも発症のリスクがあります。働き盛りの40代で、認知症と診断された男性。消えていく記憶を繋ごうと、妻と歩む日々を取材しました。
「死んだ方がいっそ楽かな…」40代で発症した認知症

46歳で若年性認知症を発症した下坂厚さん
下坂厚(しもさか・あつし)さん、49歳。3年前に「若年性認知症」と診断されました。若年性認知症は65歳未満で発症する認知症で、国内の患者は3万人以上にのぼります。
夫婦のいつもの朝。
「今日は仕事ですか?」(厚さん)
「私?仕事よ。いつも休みみたいに言わんといてくれる?(笑)毎日仕事です。じゃあね、気を付けてね。行ってらっしゃーい」(妻・佳子さん)
仕事にでかけた厚さんは、通勤の途中で、さっき別れたばかりの妻・佳子(よしこ)さんに電話します。
「もしもし、着きました。今日は仕事かいな?そうか、仕事ですか」(厚さん)
同じことを聞くのは、よくあること。道に迷うことも増え、毎朝30分早く家を出ては、職場近くの公園で時間をつぶします。
「通勤のバスを間違ったりすることがあるので、間違えても仕事に遅刻しないように」(厚さん)
通いなれた道でも、見ず知らずの場所にいるような不安な気分になるといいます。
「自分がどこにいるのかわからない。何回か通っている所でも周りの景色が分からないとか。真っ白になりますね、頭が」(厚さん)

20年以上鮮魚店に勤務
厚さんは現在、京都市の高齢者福祉施設でケアワーカーとして働いています。認知症を発症する前は、20年以上にわたって鮮魚店で働いていました。仕事にも自信が出てきた、働き盛りの40代。体に異変が起きたのは、まさにそんなときでした。
「お客さんの注文を忘れるとか、仕事の手順がわからなくなるとか、普段一緒に働いている従業員の名が分からなくなるというのは、明らかにおかしいなと思って」(厚さん)
認知症と診断されたのは、3年前。46歳のときでした。
「終わりと言ったらおかしいけど、何も分からなくなるとか、外を徘徊するとか、家族のことも分からなくなるとか。死んだ方が住宅ローンもなくなって、病気のことも考えなくて済むし、いっそ楽かなとか、そんなんばっかり考えていました」(厚さん)
職場でも、家でも、生活の中で“確かだったこと”が少しずつ曖昧になっていきます。掃除をしていたとき、使い終えた掃除機のコードを、上手く片付けることができなかった厚さん。佳子さんが声をかけます。

掃除機のコードの片付け方が分からない
「サンキュー。あと、コードを中に入れてほしいねん。ここを押したらコードが中に入るから…」(佳子さん)
「わかりましたよ」(厚さん)
「そこのフローリングの所をモップで拭いてくれる?」(佳子さん)
「掃除機は?かけんでええのか?」(厚さん)
「掃除機はかけてくれたやん、さっき」(佳子さん)
「すんまへん」(厚さん)
「そんな2回もかけんでいい」(佳子さん)
「きれいになった?」(厚さん)
「きれいになった、ありがとう」(佳子さん)
切なく苦しい妻の思い、支えとなった写真

厚さんの記憶を繋ぐ写真
家族や仕事とともに、厚さんの大きな支えになっているのが、写真です。
「写真ではあるんですけど、自分が見たまま、自分のそのときの記憶。今はそれが無いと、そのとき何をしていたのか分からないので」(厚さん)
消えていく記憶を、記録するために。写真で日常を切り取り、記憶を繋いでいます。撮りためた写真は、SNSや写真展で公開しています。

妻の写真には思い入れが…
「何気ないですけど、一番自分の中で思い入れがあるのは、奥さんの写真かな。奥さんがたまに『私のこと、まだ分かる?』と、半分冗談みたいに笑いながら聞いてくるんですけど、それが僕にはすごく胸に刺さるっていうか…。奥さんは、“いつかは自分のことも忘れられるんだろう”という思いでずっといるんだなと。いつか分からなくなるのかもしれないんですけど、そういうやり取りが切ないですね」(厚さん)
気丈に見える妻の佳子さんですが…。
「主人の方が、状況を受け入れて病気のことを理解している気がします。私はまだまだ、どんな風に変わっていくのかなっていう不安が、いつもどこかにはあります」(佳子さん)

2年ぶりの認知機能検査
この日、厚さんは2年ぶりに認知機能検査を受けました。
「今年は何年ですか?」(検査技師)
「何も見ずに?」(厚さん)
「そうですね。カレンダーなどもあえて隠していますので」(検査技師)
「何年やろ…2020年くらいかな…」(厚さん)
「京都は、全国で大きく分類すると何地方ですか?」(検査技師)
「何でしたっけ?…中部地方?」(厚さん)
「30から7を引くと?」(検査技師)
「23」(厚さん)
「では、23から7を引くと?」(検査技師)
「…」(厚さん)
答えに詰まってしまった厚さん。認知症の特徴は“ゆっくりと進行していく”ことです。
「やっぱり、ああやってテストで点数が出て現実を目の前に出されると、自分では分かっていても、やっぱりそうなんかという…ね」(厚さん)
診断が遅れ進行…徐々に失った「できること」

加藤正哉さんと妻の雅津美さん
認知症は、予防したり進行を遅らせたりすることはできるものの、根本的な治療法は、まだ見つかっていません。発症の仕組みもまだ分かっていないことが多く、正しい診断までに時間がかかってしまうケースもあるといいます。
加藤正哉(かとう・まさや)さん、57歳。7年前まで、外資系製薬会社で経理として働いていました。妻の雅津美(かつみ)さんが明らかな異変に気付いたのは、正哉さんが転職のために受けた面接の日でした。
「会社から電話があって、『先方さんが怒ってはる』と。『遅刻してきたのに、何の挨拶もない』と。早くに行って着いているはずなのにと思って話を聞くと『ビルには辿り着いたけど、分からなかった。余裕をもって行ったから時計を見てなかった』と。それで時間を超過していたってことなので、そこで『これはおかしいやろ』と思いました」(雅津美さん)
正哉さんは病院の心療内科を受診しますが、医師の診断は「適応障害」でした。
「担当医は、会社を退職したことによる“うつ症状”だとおっしゃって。『どうもない』とおっしゃったんです。私の一番の後悔が、そこなんです。本当は『そんなはずないやろ』と思っている自分がいるんですけど、でもきっとそのときは、ホッとしたんです。『脳がどうもないんやったら、気持的なことやったら、何とかなる』って…」(雅津美さん)

仕事の手順を書いた大量のメモ
認知症と診断されないまま、進行していく症状。「できないこと」が徐々に増えていきました。
「ノートに書いてはビリビリ破って、ポケットに入れて仕事に行かはるんです。これだけの人を迎えに行って、どこに座ってもらうという、ことを書いて。それが1時間では終わらないんです。晩ご飯が終わってから、深夜0時とか1時まで書いていました」(雅津美さん)
失われる記憶に抗うように綴られた、仕事の手順を書いたメモ。別の病院で若年性認知症と診断されたときには、発症から既に3年が経っていました。それでも一昨年の10月まで、自分に出来る仕事を続けました。

ぎりぎりまで働き続けた正哉さん
「真面目なんです。『働かなあかん』と。ありがたいことなんですけど、私を養わなあかんと。いま、ご飯を食べられなくなったとかいろいろあるんだけど、そのときの彼の頑張りを本当に尊敬しています。すごいです」(雅津美さん)
「まだできること」に希望を求めて―

職場で魚をさばく厚さん
下阪厚さんはある日職場で、大きな鯛を目の前でさばいて振舞うことになりました。
「包丁を持つのが久しぶりなので、骨が残っていたらごめんなさい。骨が刺さったら、看護師さん呼んでください(笑)」(厚さん)
みんな笑顔で大きな拍手を送ります。

認知症になっても続く“人生の旅”
下阪さん夫婦の、今の思いは―。
「診断を受けて2年にもなると、いろんなところでずっと失敗をし続けるので…。でも、ふと考えたときに、道を間違えたところで、何とか家に帰れているし。忘れたり、間違ったりもするけど、生きていく上では大きくいえば“かすり傷”みたいなもんかなって(笑)」(厚さん)
「私が支えているとは一切思っていなくて、これから先も一緒に乗り越えないといけないかなと、思っています」(佳子さん)
「で、今私の存在は分かってるやろな?」(佳子さん)
「ふふふ(笑)」(厚さん)
「もうできないこと」を憂いながら生きるのか、「まだできること」の中に希望を見出すのか。認知症になっても、人生の旅は続きます。
(「かんさい情報ネットten.」 2022年5月24日放送)
ホームページ上に掲載された番組に関わる全ての情報は放送日現在のものです。あらかじめご了承ください。