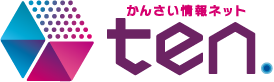3月18日(金)
「たべっ子どうぶつ」「たけのこの里」…時を超えて愛されるロングセラー菓子の新たな戦略とは!
「たべっ子どうぶつ」や「たけのこの里」など、多くの人の思い出の一部となるほど長く愛され続けるお菓子があります。そんな何十年もの間、人気を維持してきた「ロングセラー菓子」が今、次々と新たな戦略を仕掛けているというんです。一体、どんな戦略なのか…そのカラクリに迫ります!
【特集】4月から「うまい棒」が初の値上げ! 愛され続ける“ロングセラーお菓子”の新たな戦略とは?

ことし4月から「うまい棒」が10円から12円に値上げ
子どものころ、ワクワクしながら手に取ったお菓子。時代が移り変わっても愛され続けるロングセラー商品は、私たちの思い出に刻まれてきました。その裏には、企業のたゆまぬ努力があったのです。そんな中、ことし、国民的駄菓子の「うまい棒」が発売以来、初めての値上げを発表し、巷に衝撃が走りました。さらに、ちびっこの定番ビスケット「たべっ子どうぶつ」は、新たな商品展開で若者の心をわしづかみに!お菓子のブランド価値を守るため打ち出した秘策とは!?何十年もの間、人気を維持してきたお菓子が今、存続をかけて、次々と新たな戦略を仕掛けています!
うまい棒 4月から値上げへ!43年の歴史で初

うまい棒
年明け早々、1本10円でおなじみの国民的駄菓子「うまい棒」が4月から12円に値上げされるという衝撃のニュースが巷を駆け巡りました。
(4月1日出荷分より希望小売価格(税抜き)10円→12円)
発売から43年の歴史の中で初めての値上げです。主な原料であるコーンの価格や物流コストなどが大幅に上昇したために値上げに踏み切ったということですが、街で話を聞いてみると、うまい棒にはみなさん、それぞれに思い出があるようです。
「駄菓子屋行って 残り10円何買おうってときとかけっこう重宝した」
「いろいろコストがかかる中で販売価格を維持していたのはすごい」
「努力してくれてたんだなと。私たちが小さいころから10円だから、すごいなと思う」
などなど、聞こえてきたのは40年以上、「1本10円」を守り続けてきたメーカーへの称賛でした。うまい棒が生まれたのは1979年。当時はインベーダーゲームが大流行していた頃。それから40年ほどで、大卒の初任給はおよそ2倍になりました。
若者の“食べっ子離れ”を打開せよ!「たべっ子どうぶつ」の新戦略とは?

10代~20代を中心に人気のたべっ子どうぶつのグッズ
ロングセラーのお菓子が存続している裏には、どのような企業の努力や戦略があるのでしょうか。1978年に誕生した「たべっ子どうぶつ」は、グッズ展開に販路を広げ、今、若者たちから注目を集めています。パッケージに描かれている動物たちをキャラクター化し、ぬいぐるみや、タオル、トレーナーに靴下と、実に様々な商品を発売。「だがし夢や」イオンモール京都桂川店の坂根夕貴店長によると、SNS等で人気が出ており、主に10~20代の若い女性が購入しているといいます。店を訪れた若者たちに、たべっ子どうぶつのイメージを聞いてみると、「おいしい」ではなく、「かわいい」の声が続出!そこには、たべっ子どうぶつを製造するギンビスの戦略がありました。
「皆さん子供のころは食べていたのが、小学生くらいになると一度食べなくなってしまって、また親になって、『そういえば!』と手に取ってもらう方が多かったので10~20代のターゲット層に購入いただけていない状態でした。」(ギンビス 坂井明野さん)
ちなみに、もともと動物たちのキャラクターを打ち出す想定ではなかったため、名前も性別も決まっておらず、「ぞうさん」「うさぎさん」などと呼んでおり、ライオンについては、雄を示すたてがみがあるので「らいおんくん」と呼んでいるそうです。
「たべっ子どうぶつ」のルーツとなったお菓子があった!

(左)「たべっ子どうぶつ」のルーツとなったお菓子「動物四十七士」(右)たべっ子どうぶつ
40年の時を経て脚光を浴びる動物たち。実は、ルーツになったお菓子がありました。それが、「動物四十七士(どうぶつしじゅうしちし)」という47種類の動物の形をしたビスケットです。こちらも、表面には各動物の英名が印字されており、食べっ子どうぶつと比較すると、ふっくらと厚みがある形状をしています。現在は販売を終了していますが、発売は1969年。その9年後に誕生したたべっ子どうぶつは、薄焼きにするため、材料の配合や製造方法を工夫したそうです。実は、ルーツのビスケットで47種類いた動物が、たべっ子どうぶつでは46種類に。なぜ一匹だけ、減ってしまったのでしょうか?
「コアラがいなくなってます。たべっ子どうぶつを作る際に、かなり薄焼きにした都合で、コアラの耳がとがっていて割れやすくなってしまったので、泣く泣く、いなくなってしまったんです。」(ギンビス 坂井明野さん)
ギンビスでは、動物たちを使う権利を貸し出すライセンス事業を展開。動物園や服飾メーカーなど、さまざまな企業とコラボした商品が誕生し、私たちが生活の中で目にする機会が増えています。
「発売から味やパッケージをほとんど変えていない商品で、今後もそれはずっと守っていきたいと考えているので、手を加えるのは商品の味や中身ではなくて、パッケージのキャラクターたちに活躍してもらおうという方針です。お菓子についてもグッズが話題になったことで、かなり売り上げも好調に伸びていて。新たに10~20代の方も購入していただいています。」(ギンビス 坂井明野さん)
グッズがお菓子の宣伝となり、味を変えないまま、より幅広い世代に愛される存在になっているのです。
(※「動物四十七士」は今年2月末に生産・出荷を終了。現在は販売していないが、販売状況によっては在庫があり販売している可能性もある)
「きのこたけのこ」だけじゃなかった!幻のお菓子「すぎのこ村」とは?

きのこの山 たけのこの里
数多くのチョコレート菓子をヒットさせてきた明治。その代表格のお菓子が、1975年発売の「きのこの山」と、1979年発売の「たけのこの里」。2つのブランドあわせて年間240億円(2020年度 年間売り上げ)もの売り上げを誇る人気商品ですが、実は、かつて兄弟ブランドが存在したんです。それが明治の2大看板に続いて1987年に発売された「すぎのこ村」。しかし、なかなか売れず、数年で販売が終了してしまいました。棒状のビスケットに、アーモンドがちりばめられ、チョコレートがコーティングされた「すぎのこ村」。よく見ると、別のメーカーの、あのお菓子に似てるような・・・・。なぜ、売れなかったのか、明治マーケティング本部の船山慶さんに話を伺いました。

すぎのこ村 ※現在販売されていません
「お客様にとっては既視感がある形状だったかもしれない。特に独自性という部分では欠けていたかなと思います。」(明治マーケティング本部の船山慶さん)
日々、多くの新商品が登場しますが、定着するのは“ひと握り”。きのこの山、たけのこの里が客の目を引いたのはその独特な“形”でした。きのこの山の形はすでに明治が発売していた「アポロ」がヒントになったそうです。
「アポロが発売当時なかなか販売が芳しくなく、工場のラインの生産性を高める必要がありました。そのときにアポロにカシューナッツを刺したら、きのこみたいに見えるという案が出たんです。」(明治マーケティング本部の船山慶さん)
カシューナッツは形がバラバラで、大量生産に向かないため、軸はクラッカーに変更。丸みのある三角形のきのこ部分と、ちょこんと刺さったクラッカーのかわいらしい形が受け入れられ40年以上、人気を維持してきました。
形を見ればお菓子がわかる!?「きのこたけのこ」ブランドを守る新戦略

「きのこの山」「たけのこの里」を立体商標として登録
「きのこの山」、「たけのこの里」の存続をこれからも維持すべく、技術的な面や商品名など、他社に権利を真似されないように守るため、二つのお菓子は「立体商標」として登録されています。商標とは、他社の商品と区別するためのもので、登録されれば、模倣から守ることができます。例えば、ロゴを登録する「文字商標」、キャラクターなどのデザインを登録する「図形商標」などがありますが、ほかに、「音商標」も登録可能で、コマーシャルの冒頭や最後に企業名を音階に乗せて流しているのも、これにあたります。久光製薬のコマーシャルは、「ヒ・サ・ミ・ツ」の企業名を「ミ・ラ・ミ・ファ♯」の音階で流し続けること30年以上!聞く人にブランドの印象を強く残してきました。そこで、お菓子のブランドイメージを保つため、明治が目を付けたのが形を登録する“立体商標”だったのです。明治・知財戦略部の長尾美紗子さんによると、
「きのこの山・たけのこの里は今までにないような新しい形状の商品がヒットしたと考えているので、立体商標として登録することで商品名が違っても形が似た商品に対して権利を守ることができるようになります。」(明治・知財戦略部 長尾美紗子さん)
2018年に「きのこの山」、去年7月に「たけのこの里」が登録されましたが、そこに至るまでには、およそ20年もの長い年月がかかりました。1997年に2つのお菓子を申請しましたが、ありふれた「普通の形」という判断で登録は認められませんでした。立体商標は、その形を独占できてしまう権利のためハードルが高いのです。登録する術を模索し続ける中、明治が取った方法がお客へのアンケートでした。
「1200名以上に、きのこの山、たけのこの里についての調査を行って、それぞれ9割以上からどんな商品かわかるかというアンケート結果を得ています。一般のお客様が何の商品かわかるようになったものは例外的に登録が認められます。」(明治・知財戦略部 長尾美紗子さん)
この形といえば“きのこの山”、“たけのこの里”と、すでに認識されていると証明し、お菓子としては珍しい立体商標への登録を果たしました。
「お菓子の業界には多くのロングセラー商品がありますが、今回の立体商標登録によって、お菓子業界の方々にもお菓子の形を守ることを考えてもらうきっかけになるのではと思っています。」(明治・知財戦略部の長尾美紗子さん)
愛される理由は味だけにあらず。お菓子の世界観を守って人気を維持し、甘い思い出を作ってきたロングセラーお菓子。その裏には甘くない企業努力が隠れていました。
(読売テレビ「かんさい情報ネットten.」2022年3月18日放送分)
ホームページ上に掲載された番組に関わる全ての情報は放送日現在のものです。あらかじめご了承ください。