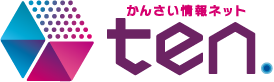3月8日(火)
【南海トラフ】“災害”で人生を“断絶”させない備えとは
南海トラフ巨大地震に備え、今自治体で作成が進んでいるのが「事前復興」の計画です。「事前復興」とは、災害が起きた後、住宅地をどこに再建するかなど、被災前から作っておく町の復興計画です。
その狙いと課題をゲキ追しました。
(かんさい情報ネットten. 2022年3月8日放送)
【特集】“南海トラフ巨大地震”に備えて作成進む「事前復興」計画 被災前に考える「災害で人生を“断絶”させない」備えとは?

発生の切迫性が高まっている南海トラフ巨大地震
南海トラフ巨大地震に備え、今自治体で作成が進んでいるのが「事前復興」の計画です。「事前復興」とは、災害が起きた後、住宅地をどこに再建するかなど、被災前から作っておく町の復興計画のことを言います。その狙いと課題を取材しました。
南海トラフ巨大地震へ向けた意識の高まり

和歌山県田辺市
和歌山県南部に位置する田辺市。南海トラフ巨大地震が起きると、津波(高さ1メートル)が約12分で到達し、最大で12メートルに達します(県の想定)。
(田辺市新庄町に住む橘智史さん)
「避難広場は高さが18メートルぐらいあるので、ここから見える住宅地は、ほぼ浸水すると想定されています。」

1946年昭和南海地震 津波で破壊された田辺市
田辺市新庄町に住む橘智史さん(51)。この町で生まれ育ち、いつ来るか分からない津波の脅威と向き合ってきました。この町には津波に襲われてきた歴史があるからです。76年前におきた昭和南海地震。写真には、津波で破壊し尽くされた町の様子が克明に記録されています。こうした南海トラフを震源とする大地震は、おおむね100年から150年の間隔で繰り返し発生してきました。今後40年以内の発生確率は、90パーセント程度とされています。11年前の東日本大震災は、南海トラフ巨大地震への備えを再認識するきっかけになったといいます。
(橘智史さん)
「家族でもそうだし、地域でも、とにかく高台に逃げようという話はしています。3.11の東日本大震災以降、現実を見ることによって、何とかして生きなければ、逃げなければという意識は高まっています」
被災前に備える「事前復興」計画とは

新庄地域の地形を再現した模型
そんな中、この町で新たに始まった取り組みがあります。
(上馬場雄介記者)
「公民館の一角に和歌山大学らの学生たちが設置しているのは、新庄地域の地形を忠実に再現した模型です」
(和歌山大学 平田隆行准教授)
「『事前復興』の計画を住民の皆さんに展示しています。例えば、浸水域を安全な高さにまでかさ上げするとか、山を少し切って住宅団地を作るとか、暮らしやすい町ができないかと検討しています」

「事前復興」計画とは
「事前復興」計画とは、地震や津波で被災した後、いち早く復興できるよう、あらかじめ住民や自治体が作る「まちづくりの基本的な方針」や「復興の手順」などの計画のことです。がれき置き場や仮設住宅をどこに設置するのか、住宅地を現地でかさ上げするのか、それとも高台に移転するのかなど、事前に話し合って共有するものです。
県内の4自治体で計画づくりに関わり、新庄地域の計画づくりを支援している和歌山大学の平田准教授は、その必要性を訴えています。
(和歌山大学 平田隆行准教授)
「発災した後に(復興計画を)考えて、いろんな議論をして話し合って将来の姿を共有していくのは、すごく時間がかかってしまう。いち早く復興を進めていくためには将来のイメージを持っておくことが必要だと思っています」
今回の計画案は、学生らが住民に聞き取りを重ねて作成。住宅地や商業施設を開発する場所、手を加えずに自然の風景を維持する場所など、復興後の町の姿が詳細に記されています。

新庄地域の「事前復興」計画案
(住民)
「マンションみたいに集合(住宅)で移転する考えはないの?」
(学生)
「(全ての住宅が)集合で動くことは考えていなくて、元の(住宅地)部分もしっかりかさ上げする。元々のところに住みたい方も多いのではないかという考えです。」
(橘智史さん)
「こういう考え方は自分たちではできない。理想と言えば理想だし、(被災後は)現実に出来るように努力できたらいいなと思う」
「事前復興」計画はほかの町でも

県が策定した「事前復興」計画づくりの手引き
和歌山県は4年前に、「事前復興」計画づくりの手引きを策定。「復興に時間がかかりすぎると地域の活力が失われる」として、沿岸の19市町に、計画の作成を呼びかけています。 (※美浜町は作成済)

「事前復興」計画を検討 和歌山県みなべ町
田辺市に隣接するみなべ町でも、ことし1月、 「事前復興計画」を検討する委員会の初会合が開かれ、住民と町の職員らが意見を交わしました。
(コンサルタント)「みなべのICや役場などの主要拠点が浸水するようなエリアだから、公共施設などは高台に移転した方が良いのではないか。」
しかし、初めて耳にする「事前復興」という言葉に、戸惑いを隠せない住民も多いのが現状です。
(住民)「正直言ってまだ壊れていない町が壊れたときのことを考えて復興する。ものすごく想像力がいる。例えば東北のどこそこの町はこうなったとか、どこそこの漁港はこうしたとか、成功例や成功しなかった例を示していただくくとイメージが持ちやすい」
Q:「事前復興」という概念は聞いたことがあった?
(住民)「初めてです。想定しておくことは転ばぬ先の杖だろうが、住民がそこまで受け止めて前向きになるには、だいぶ準備が欲しい」
(住民)「避けられないと思う南海トラフ地震は。きのうも夜中に地震があって、いつ(来る)かなと怖いので、起こる前にいろいろと計画しておくことは大事だと思います。」
「事前復興」 ルーツは阪神・淡路大震災

27年前から提唱されていた「事前復興」
「事前復興」の考え方は、決して新しいものではありません。実は、27年前の阪神・淡路大震災の発生後、専門家によって提唱されていました。私たちが訪ねたのは神戸市兵庫区の松本地区。広い道路のまわりに住宅が整然と立ち並び、人工のせせらぎが流れる、落ち着いた景観の町です。中島克元さん(66)は、震災で被災しながらも、この地区のまちづくりに大きく関わりました。

松本地区のせせらぎ通り
Q:今は歩道と車道になっているが?
(中島克元さん)
「こんなものはなかった。道が狭くて、家ばかりが建っていました。」

被災した町の復興に時間がかかった
松本地区では、建物の約8割が焼失。市は、震災から2か月後に、「土地区画整理事業」を行うことを決めましたが、新たに道路や公園を作るため、自分の土地を取られることに反対する住民も多かったといいます。中島さんは、住民らでつくる協議会の会長として、意見をまとめようと奔走しました。まちづくりの計画がまとまり、「土地区画整理事業」に着手した時には、すでに震災から2年近くが経っていました。中島さんは、「被災直後は、精神的な余裕がなかった」と振り返ります。
(中島克元さん)
「あの頃は賛成する人も反対する人もみんながパニックだから、その中で言いたいことを言っていた。災害が起こる前に復興計画は作っておくもの。」
東北で起きた“人口流出”を防ぐために

東北で起きた“人口流出”を防ぐために
平田准教授とともに「事前復興」に取り組む和歌山大学の宮定特任准教授は、「東日本大震災の被災地のまちづくりも、厳しい現実に直面している」と指摘します。
(宮定章特任准教授)
「宮城県石巻市雄勝町では、海から離れたところに山を切り開いて町を作ることになったが、海の近くに住んでいた方で、『海から離れた高台に行くんだったら、都会に出ていく』という方が結構いて、人口減少が起こってしまった。」
住民同士や住民と行政との合意形成に時間がかかるうちに人口が流出し、高齢者だけが取り残されるという問題は多くの東北の被災地で起きています。「事前復興」は、復興のスピードを早めることで、人口流出を防ぐことを狙いとしています。
(平田准教授)
「“人生が途中で断絶しないこと”が非常に大切だと思っています。災害に遭って何が悲惨かというと、思ってもいない人生になってしまうことが一番良くない。そうならないように、災害が来たとしても、『こうなると思っていた』と想定内に収めていくような人生の組み立て方ができるようにする。それが「事前復興」でできれば、非常に良いのではないかと思います。」
「事前復興」に立ちはだかる壁

「事前復興」の“先進地“由岐湾内地区
住民主体で「事前復興計画」をつくり上げた町があります。徳島県の南東部、人口約1000人の美波町由岐湾内地区。和歌山県の沿岸部と同じく、津波による破壊と再生を繰り返してきた町です。

地区内には複数の津波避難階段がある
(美波町由岐支所 浜大吾郎さん)
「この津波避難階段は、一番上まで上ると高さは30メートル以上。南海トラフ巨大地震の津波は想定の高さが12.3メートルなので、想定外の高さの津波にも備えたような設計になっています」

地元の小学生が作成した“未来のまち”
この地区は南海トラフ巨大地震の津波で、99パーセントの建物が浸水すると想定されています。町職員の浜さんによると、安全を求めて町を出る若者も多く、被災前に過疎化が進む “震災前過疎”に拍車がかかっているといいます。こうした状況を受け、住民らは、東日本大震災の翌年から「事前復興」計画の作成をスタート。次世代に継承したい町の魅力や今後のまちづくりの方針を話し合ってきました。中でも、安全な住まいを最大のテーマとして、高台に住宅地を整備し、若者に先行して移転してもらうことを決めました。

計画通りに進まない事業
しかし、その整備は進んでいません。ニーズがあるかわからないとして宅地開発業者は及び腰で、町の財政に余裕はありません。また、国の「防災集団移転促進事業」などの制度は、建築制限をともなう災害危険区域の指定が必要となり、住民の混乱を招くため、被災前に利用するのは難しいと言います。計画はあっても事業は進まず、地震発生のタイムリミットが迫るだけの状況に、住民らは気を揉んでいます。
計画の作成に協力し、自らもこの地区に移住した徳島大学の井若研究員は、「『事前復興』に取り組むことは、町が抱える課題に向き合うことでもある」と指摘します。
(徳島大学 井若和久学術研究員)
「『事前復興』は地域づくりなので、地域を住民みんなでもう一度見直して、どういうふうにして人のつながりをつくっていくかを考えるきっかけになるし、その方が地域にとっては優先順位が高い。そこで住み続ける意味を自分や地域の中で考えることになるので、魅力も課題も含めて地域と向き合う機会になる。」
まちの未来のあるべき姿を考え、一日も早い復興につなげる。過去の大災害から得た教訓を生かすための模索が続いています。
(かんさい情報ネットten. 2022年3月8日放送)
ホームページ上に掲載された番組に関わる全ての情報は放送日現在のものです。あらかじめご了承ください。