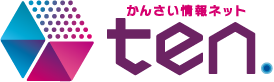3月24日(金)
難病を抱えての子育て 「倦怠感で子どもを送り迎えできない…」懸命に家族に向き合う『全身性強皮症』のママ
「関節が痛み赤ちゃんを抱けなかった」「体調が悪いと子どもの送り迎えもできない」…様々な葛藤を抱えつつ、闘病しながら子育てをする親たちがいます。全身の皮膚が徐々に硬くなる「全身性強皮症」と闘いながら姉妹を育てる女性は、周囲のサポートを得ながらなんとか育児を乗り切っています。しかし、体だけでなく心にも負担が…。1歳で関節が痛む「小児リウマチ」と診断された女性は、兄弟を育てる中で孤独や「周囲の理解不足」を感じました。その経験を糧に、闘病しながら子育てをする親が悩みや情報をわかちあえる団体「てくてくぴあねっと」を立ち上げました。難病を抱えながら懸命に子育てをする親の実情を知ってほしい―。親たちの思いを取材しました。
【特集】全身の皮膚や内臓が硬くなる…体が痛むと子どもを抱けない…子どもとの未来を諦めない、難病と闘いながら子育てをする親の実情

病気を抱えながら子育てをする中里亜矢子さん
国が指定する難病の患者は国内に少なくとも102万人いますがその中には、長い期間、治療を続けながら子育てをする人もいます。中里亜矢子さんは、夫とクライミングを通して親しくなり結婚、出産しました。しかし、亜矢子さんは難病になりクライミングはできなくなりました。今は病気を抱えながらの子育てですが、支援も社会の理解も十分とはいえません。子どもとの未来を諦めない、難病と闘いながら子育てをする親たちの実情とは。懸命に家族と向き合う、親たちの思いを取材しました。
全身の皮膚や内臓が硬くなる難病と闘うママ

病名は「全身性強皮症」
中里亜矢子さんは、7歳と8か月の二人の娘を育てています。病気のため、週に2・3回、朝と夕方の1~2時間、ヘルパーの支援を利用していて、家事や育児の支援、ミルクの準備や子どもたちの身支度、送り出しをサポートしてくれます。 亜矢子さんの病名は「全身性強皮症」で、長女を生んだ3年後に診断されました。手足の指先から徐々に全身の皮膚や内臓が硬くなる、国が指定する難病で、血流が悪くなって指先がしびれたり潰瘍ができたりして、夜眠れなくなるほど痛みます。見た目にはわかりにくいのですが、亜矢子さんの筋力は70代から80代だと診断されました。体は、つねに鉛のように重い状態です。全身性強皮症は遺伝性のない病気で、長女がきょうだいを何年も心待ちにしていたこと、主治医と何年も身体の状態を相談しながら、許可が出てから二女の出産に踏み切りました。
まだ幼い子のため、野菜をすりつぶすなど、離乳食づくりは体力を使いますが、手を抜かず休み休み作業を続けます。しかし立っていることができなくなり、料理の途中でヘルパーに代わることもあります。子どもの栄養面に気を遣っておかずを1品増やせるのは、ヘルパーのサポートのおかげです。亜矢子さんは、「ヘルパーさんのおかげで体をセーブできるというか、本当に助かっています」と話します。

自己負担額は毎月5万円以上
二女を保育園に通わせたくても、近くに空きはありません。離れた場所で探しましたが、体力的に車の運転が難しく、車での送迎は公的な「育児支援」とみなされないため、通わせることはできていません。
また、この病気に根本的な治療法はなく通院が続くため、経済的な負担も少なくありません。医療費と公的支援にかかる自己負担額、交通費などを合わせると、毎月5万円以上かかります。

亜矢子さんは、難病と診断される前はクライミングが趣味で海外を飛び回っていました。亜矢子さんは「クライミングはライフワークだったので、奪われたという気持ちが本当に強かった。過去の自分にずっとしがみついていた」と話します。
今は両親の助けも借りて、なんとか日々を乗り切っています。

相談支援の専門員 河西恵美子さん
(亜矢子さん)
「(ヘルパーの支援は)週2回の朝夕だけだと足りなく感じていて。自己負担額がかかってでも、増やしたいと思っています」
話を聞く相談支援の専門員の河西恵美子さんは、亜矢子さんの体の負担はもちろん、心の状態を気にかけていました。この日、河西さんは、一枚のパンフレットを亜矢子さんに渡しました。

「多言語パートナー」のパンフレット
(河西さん)
「こんなのも見つけたんだけど。興味があるかな?」
パンフレットの見出しを見た亜矢子さんはすぐに反応しました。
(亜矢子さん)
「『多言語パートナー』…へーどういうことですか?」
(河西さん)
「北広島市が仲介しているボランティアで…」
内容に目を通した亜矢子さんは即答します。
(亜矢子さん)
「ぜひやりたいです」
河西さんは、心が前を向けるように、亜矢子さんが得意な英語を生かせるボランティアを紹介しました。亜矢子さんには、無理をしすぎないように、自分のペースを見つけていくことが必要でした。

感謝の気持ちを語る亜矢子さん
(亜矢子さん)
「客観的にみてくれているのが分かるんです。家族にも言えない悩みとかも、河西さんに言えたりするので…。長女を生んだときはまだ病気が発覚していないし、今よりも全然動けていたので、できることが今よりもすごくあったんですけど、病気が発症してからの子育ては全然違うと、妊娠のときから思っていて。周りにサポートしてもらって申し訳ない気持ちがすごくあって、でもサポート受けないと娘のことも守れない…」
亜矢子さんは涙ながらに語りました。
関節リウマチと闘うママ “難病のお母さん”を知ってほしい

うえやま・みかさんと二人の子ども
松葉づえをつきながら、2人の子どもを連れて歩くのはうえやま・みかさん。6歳と2歳の兄弟を育てています。うえやまさんは、1歳のときに小児リウマチを発症しました。自己免疫の異常で関節が痛み、移動には松葉づえが欠かせません。遊び盛りの兄弟の動きについて行くのは難しい状態です。
(うえやまさん)
「対応できるところと、できないところがあるから、我慢させてしまうのが悪いなと思うんですけど…」

難病の親を支える団体「てくてくぴあねっと」
うえやまさんは、2021年11月、難病を抱えながら子育てをする親を支える団体「てくてくぴあねっと」を立ち上げました。この日は、NPO法人「チャリティーサンタ」から寄付された絵本を16の家庭に届けるため、梱包などの作業をします。症状が悪化すると減ってしまいがちな親子の時間を作ってもらうためです。
難病を抱えていても、わが子を思う気持ちはみんな同じです。

思いを語るうえやまさん
うえやまさんがこの活動を始めたのは、過去に保育園でかけられた言葉がきっかけでした。
(うえやまさん)
「以前、保育園のスタッフに『保育園は就労された人たちのものなのよ』『お母さん、おうちで寝ているだけですよね』というようなことを言われて。すごく追い詰められたことがあったんです。調べたら、そういうふうに言われて『肩身が狭い』という難病のお母さんもたくさんいたので、もっといろんな人に“闘病中のお母さん”を知ってもらえたら、なんとかなるのかな、という思いもあって活動をはじめました。」
重症度や家庭の状況などによってヘルパーによる育児支援を受けられるか決まりますが、同居する夫がいるうえやまさんの場合、利用するのは難しい状況です。子育ては楽しい。でも、体が痛み、泣いている子どもを抱けない日もありました。難病は治療が長く続くため、将来子どもをヤングケアラーにしてしまうのではないかと不安を口にする親も少なくありません。

ヤングケアラー研究の専門家
(大阪歯科大学 濱島淑恵教授(当時))
「ヤングケアラーの話をするときに、親の批判に向かうことが多くて『親は何をしているのか』という話をされるときが多い。親がしんどいから子どもが手伝っているので、親子を支援する必要がある、ということへの理解が広がればいいなと思います」
大切なのは少しずつでも歩み寄ること、見えにくいからこそ知ること

「てくてくぴあねっと」のオンラインカフェ
悩みや情報をわかちあう場もうまれています。亜矢子さんは、去年秋から、「てくてくぴあねっと」のオンラインカフェで、同じように難病と闘いながら子育てをしている親たちとつながり始めました。
亜矢子さんが、オンラインカフェで知ったのは、ひとりじゃない、ということ。この気持ちが病気を受け入れる一歩になりました。
この日、単身赴任をしている夫が、帰ってきました。
(夫)
「病気と闘っているのもそうだし、体力がない状態でもやってくれているのは、すごいことだしありがたいなと思っています。その分、平日、仕事をがんばらないと顔向けできない」
亜矢子さんの自宅にはクライミングの壁が付いていて、登れるようになっています。自宅にこの壁をつくることはふたりの夢でした。
(夫)
「ようやく最近、亜矢子も動けるようになってきて、亜矢子が持ちやすいようにつけて、ぐるぐる回れるようにいつかなればいいな」
亜矢子さんもがんばれば、いつか登れるのではないか、と夫は考えています。
亜矢子さんは、いつも前向きな夫に対し伝えられていない思いがありました。難病とともに、家族の未来をどう描いていくのか。亜矢子さんは思い切って、気持ちを打ち明けました。
(亜矢子さん)
「恥ずかしいんだけど…。この場を借りて伝えたいことがあります。二人のことを考えたときにクライミングは欠かせないもので、よく3度の飯よりクライミングが好きだと話をしていたよね。海外のいろんな岩場にクライミングトリップしようと、それを目標に日々を送っていたので、病気になったときに、それができなくなってごめんねという気持ちでいっぱいでした。まさか自分が難病患者になるなんて思いもしませんでした。病気になる前にふたりで思い描いていた未来とは違ってしまったかもしれないけど、新しい形で家族4人の道を歩んでいけたら幸せです。いまだに自分の気持ちを言葉じゃなくて態度だけで伝えてしまうことがあるので、これからは冷静に言葉にして伝えていきたいと思っています。出会ってからきょうまで、そばにいてくれて本当にありがとう」
(夫)
「こちらこそありがとう…。気力でなんとかがんばれたら、なんか変わるかな、と期待に込めている部分もあって、それが(妻にとって)プレッシャーになっていたり…まず伝えてくれたから気持ちが少しわかったので」
大切なのは、少しずつでも歩み寄ること。見えにくいからこそ知ることが、難病を抱えながらの子育てを理解する第一歩かもしれません。
(「かんさい情報ネットten.」2023年3月24日放送)
ホームページ上に掲載された番組に関わる全ての情報は放送日現在のものです。あらかじめご了承ください。